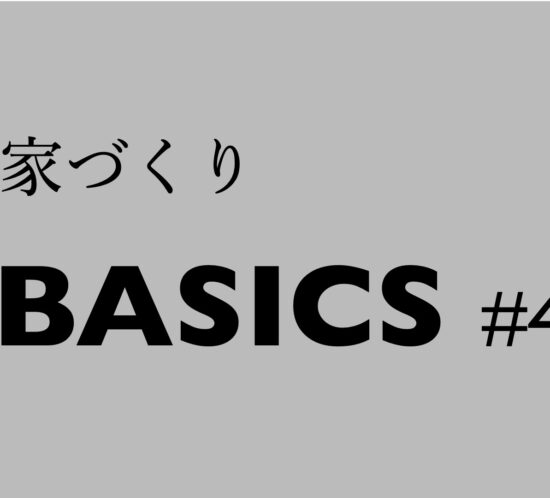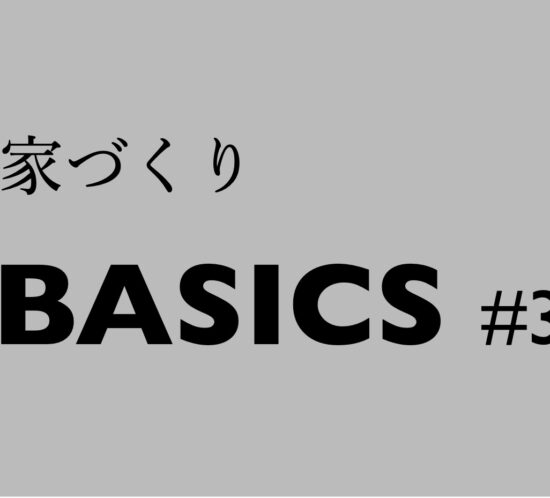予算は「決める」ものではなく「使い方を選ぶ」もの
家づくりの相談で、よく聞くのが「予算は○○万円くらいで考えています」という言葉です。 家づくりを考え始めると、「結局、全部でいくらかかるのか」「そのうち、建物にはどれくらい使えるのか」が気になるのは、とても自然なことだと思います。 ただ実際には、予算は金額そのものよりも、どう使うかの方が重要です。 予算は「上限」を決めることではない 予算というと、「ここを超えないようにするライン」として考えられがちです。 けれど本来の予算は、どこにお金をかけ、どこを抑えるかを選ぶための道具です。 前回のBASICS #3では、トップ3・下位3・NGというかたちで要望を整理しました。この整理ができていると、予算の話は「削る」から「振り分ける」に変わります。 まずは「家づくりの総額」を知る 予算を考えるうえで、最初につまずきやすいのが建物価格だけを見てしまうことです。 家づくりには、建物本体以外にもさまざまな費用がかかります。 家づくり総額と内訳の目安(土地代を除く) 家づくりにかかる費用を100%とした場合、おおよそ次のような配分になることが多くなります(※地域や敷地条件によって前後します)。 建物本体工事費:60〜65%設計料:8〜12%外構工事:7〜12%地盤改良・基礎調整:0〜10%諸経費(申請・検査・登記・各種負担金など):5〜8% 特に諸経費は、インフラ条件や法規、敷地条件によって想定より増えることが少なくない項目です。 総額別|建物本体にかけられる金額の目安 上記を前提にすると、建物本体に使える金額は、総額の約6割前後と考えるのが現実的です。 総額 3,000万円 → 建物本体 約1,800〜1,950万円総額 3,500万円 → 建物本体 約2,100〜2,275万円総額 4,000万円 → 建物本体 約2,400〜2,600万円総額 4,500万円 → 建物本体 約2,700〜2,925万円 「思っていたより建物に使えない」と感じる方も多いですが、ここを甘く見てしまう方が、後で苦しくなります。 坪単価について(建築家住宅の場合) 予算の話になると、「坪単価はいくらくらいですか?」という質問もよくいただきます。 結論から言うと、建築家に依頼する住宅の場合、坪単価は少なくとも130万円前後から見ておくのが現実的です(※ここでは建物本体工事費を想定しています)。 現在の感覚としては、次のようなレンジになります。 130〜150万円/坪 → 建築家住宅としての標準的なゾーン。 構造・断熱・納まりをきちんと押さえ、 空間の質を成立させるライン。 150〜180万円/坪 → 素材選定や空間構成に明確な意図がある場合。 敷地条件が厳しいケースも含まれます。 180万円/坪〜 → 構造・素材・環境性能に強いこだわりがある場合や、 難易度の高い敷地条件を前提とする住宅。 同じ坪単価でも、何にお金を使っているかは設計によって大きく異なります。 工事費は、上がり続けています ここ数年、住宅の工事費は下がることなく、緩やかに上がり続けているのが実情です。 ・資材価格の上昇・人手不足による労務費の上昇・施工体制の変化・性能・基準の引き上げ これらが重なり、以前と同じ家を、同じ金額でつくることは難しくなっています。体感としては、急に跳ね上がったというより、毎年少しずつ確実に上がっているという印象に近いかもしれません。 だからこそ「何を大切にするか」が重要になる 工事費が上がっていると聞くと、「早く建てないと損なのでは」と感じる方もいます。ただ、焦って判断してしまうと、本来大切にしたかったことが抜け落ちてしまうこともあります。 重要なのは、今の相場感をきちんと知ることその中で、何を優先するかを整理すること工事費が上がり続けている今だからこそ、要望と予算の整理が、以前よりも重要になっています。 トップ3は「お金を使う理由」になる BASICS #3で整理したトップ3は、そのまま予算配分の優先順位になります。 ・家族が自然に集まる場所を大切にしたい・外とゆるやかにつながる居場所がほしい・一人で落ち着ける時間を確保したい こうした要望が明確であれば、面積、天井の高さ、光の取り入れ方など、どこにお金を使うかの判断がしやすくなります。 下位3は「調整のための余白」になる 一方で、下位3は予算調整の場面でとても重要な役割を果たします。 条件によって優先度を下げられる要望が整理されていると、予算調整が「我慢大会」になりません。 どこから調整すればいいかが分かることが、大きな安心につながります。 予算の話こそ、建築家と一緒に 予算は、一人で決めきるものでも、誰かに丸投げするものでもありません。 要望を整理したうえで、建築家と一緒に「使い方」を考えていくことで、数字は具体的な空間の話へと変わっていきます。 初回相談について 初回のご相談では、想定している家づくりの総額建物本体にかけられる金額の目安要望とのバランスを、現在の相場感を踏まえて一緒に整理します。 予算感がまだ固まっていなくても、土地が決まっていなくても構いません。 まとめ 予算は、夢を削るための数字ではありません。 ・何を大切にするかを形にするためのもの・使い方を選ぶための道具 工事費が上がり続けている今だからこそ、数字から逃げず、同時に数字に振り回されないことが大切です。 次回は、この予算感を踏まえて 家づくりBASICS #5「土地の選び方」 へ進みます。 家づくりBASICS シリーズ これまでの「家づくりBASICS」は、こちらからご覧いただけます。 家づくりBASICS #1|家づくりの進め方(全体像) ▶︎[https://ikd-a.com/2025/10/17/iedukuri_1/] 家づくりBASICS #2|家づくりのパートナーの選び方 ▶︎[https://ikd-a.com/2025/12/19/iedukuri_2/] 家づくりBASICS #3|土地探しの前に要望整理 ▶︎[http://ikd-a.com/2026/02/06/iedukuri_4/] 順番に読んでいただくと、家づくりを考えるときの整理の仕方が、より立体的に見えてくると思います。